性感染症
性感染症とは
性感染症とは性的接触を介して人から人へ感染する感染症で、梅毒、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)などがあります。
感染経路:粘膜や皮膚から感染します
性的接触により、口や性器等の粘膜や皮膚から感染します。また、オーラルセックス(口腔性交)やアナルセックス(肛門性交)などでも感染します。
感染すると
かゆみや痛み、発疹といった様々な症状がみられます。感染症によっては、未治療のまま放置すると、神経や心臓などに深刻な合併症や後遺症を残すことがあります。
また、感染によって粘膜が傷つきやすくなることで、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)などの感染症にかかる可能性が高まります。
妊娠可能な女性や、妊娠中の女性が性感染症にかかった場合、母子感染により先天性の障害の原因となり、さらに未治療のまま放置すると障害が残る可能性もあります。また、不妊の原因となることもあります。
検査:医師による診察と血液検査を行います
感染しても、比較的軽い症状にとどまる場合や無症状であることもあるため、検査に結びつかないことがあります。感染が疑われる場合や、不安に感じたらすぐに検査を受けましょう。検査を受けることは、感染を広げないためにも重要です。
1.医療機関での検査
診療科は性感染症内科のほか、男性は泌尿器科、女性は婦人科、のどに症状がある場合は耳鼻咽喉科、皮膚に症状がある場合は皮膚科など、症状にあわせて受診してください。
2.保健所での検査
保健所等におけるHIV・性感染症検査・相談についてをご覧ください。
検査の詳細については直接医療機関又は保健所にご確認ください。
予防
・感染の有無が確認できない相手との性行為は避けましょう。
・無防備な性行為は避け、コンドームを正しく着用しましょう。オーラルセックス(口腔性交)、アナルセックス(肛門性交)でもコンドームは有効です。
・予防接種により予防できる感染症もあります。
注意:ピルは避妊のためのもので、性感染症の予防はできません。
治療
主に内服薬での治療となります。他にも外用薬や注射など感染症の種類や症状によって異なります。医師の指示に従い、自己判断で治療を中止することはせず、適切に治療を進めることが大切です。
その他
性感染症に関する詳しい情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。
梅毒が増えています
梅毒は梅毒トレポネーマという細菌により引き起こされる感染症で、全身に様々な症状が出ることがあります。近年、急速に感染が拡大しており、注意が必要です。男性では20~50代、女性では20代が突出して増えています。
梅毒は、検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、脳や心臓に重大な合併症を起こすことがあり、妊婦が梅毒に感染すると胎盤を通じて胎児に感染し、先天梅毒の原因となります。また、未治療の場合は流産、死産などの原因にもなります。
症状
| 期間 | 症状 | |
| 1期顕症梅毒 | 感染後数週間 |
・感染した部分にしこりや潰瘍(かいよう) ・股の付け根の部分(そけい部)のリンパ節の腫れ ・痛みがないことが多く、治療をしなくても自然に軽快する 注意:症状が軽快しても体内に病原体が残っているため、他の人にうつす場合があります |
| 2期顕症梅毒 | 感染後数か月 |
【症状が全身に広がる】 ・手のひら、足の裏、体幹などに淡い赤色の発疹(バラ疹) ・肝臓、腎臓など全身の臓器に様々な症状が出現 注意:未治療の場合、さらに進行するおそれがあります。 |
| 晩期顕性梅毒 | 感染後数年 |
・皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム種) ・大動脈瘤などの心疾患症状 ・精神症状の出現、認知機能の低下、歩行障害など 注意:複数の臓器に病変が生じ、死亡することもあります。 |
先天梅毒
梅毒にかかった母体から、胎盤を通じて胎児に感染することで起こります。
・胎児への影響:早産、死産、胎児発育遅延、心奇形、紫斑、小頭症など
・新生児への影響:難聴、失明、精神発達遅滞、緑内障など
注意:妊娠中の感染だけでなく、妊娠前から感染している場合、母子感染のリスクが高まります。
検査
感染の不安がある場合や感染が疑われる場合には、検査を受けましょう。
梅毒は保健所で匿名・無料で検査を受けることができます。
治療:早期に適切な治療を!
抗菌薬による治療となります。早期に治療を開始することが重要となるため、早めに受診をしましょう。早期発見・早期治療で完治が可能です。
予防
感染者、特に感染力の強い1期及び2期の感染者との性行為などを避けることが基本です。コンドームは予防効果がありますが、完全ではないため感染が疑われる場合には、性的な接触を控え、早期に医師の診断・治療を受けましょう。
また、一度治っても再び感染することがあるので、予防が必要です。
その他
梅毒に関する詳しい情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課感染症予防係(保健センター内)
〒367-0031
埼玉県本庄市北堀1422-1
電話:0495-24-2003
ファックス:0495-24-2005
メールでのお問い合わせはこちら
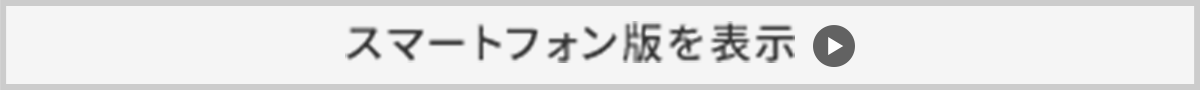







更新日:2025年09月24日