定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
以下は現時点での予定のため、変更になる場合がございますので、ご了承ください。
詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します。
概要
調整給付の「不足額給付」とは、当初調整給付(注1)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注1)令和6年度に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対して、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
支給対象者
令和7年1月1日において本庄市に住民登録があり、以下の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
〇令和5年所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
〇こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円を超える方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(注2)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注2)「低所得世帯向け給付」とは、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)を指します。
【支給対象となりうる例】
〇青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
〇合計所得金額48万円を超える方
給付額
不足額給付1
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額」との差額(1万円単位で支給)

不足額給付2
1人当たり原則4万円(注4)
(注4)・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は等は3万円
・地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額
支給手続き
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
不足額給付1の手続き
〇対象者には、以下の「支給通知書」又は「支給確認書」のいずれかを送付します。
〇通知の発送時期:令和7年7月31日(木曜日)以降、順次発送
支給通知書(市が口座情報を把握している世帯)
通知記載の口座に給付
振込日:令和7年8月27日(水曜日)
・本給付金を受給しない場合又は振込口座を変更する場合は、令和7年8月14日(木曜日)までに給付金コールセンターへご連絡ください。
支給確認書(市が口座情報を把握していない世帯)
必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。
不足額給付2の手続き
〇対象者には、令和7年8月中旬以降に通知を送付予定です。
詳細につきましては、決定次第、お知らせします。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください
市内で定額減税や給付金をかたった不審な電話が確認されています。
給付金に関して、市から電話やメールなどで銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。
不審な電話やメール、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください 。
よくある質問と回答
給付金はいつ振り込まれますか。
支給通知書(市が口座を把握している世帯)について
・振込日は、令和7年8月27日(水曜日)です。
支給確認書(市が口座を把握していない世帯)について
・受理から振込まで2~3週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理するため期間が長くなる場合があります。また、申請に不備があった場合には、さらにお時間をいただく場合があります。
なお、どちらも振込が完了しましたら、後日「振込済通知書」を送付しますので、ご確認ください。
振込済通知書を受け取っていますが、入金がありません。
振込済通知書に記載の口座を再度ご確認ください。入金が確認できない場合は、給付金コールセンターへご連絡ください。
なお、振込依頼人名は、「ホンジョウチョウセイ」と記載されます。
申請はいつまで受け付けてくれますか。
申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)です。
書類を紛失しました。再発行はできますか。
再発行可能です。給付金コールセンターへご連絡ください。
書類を書き損じました。どのように対応すればいいですか。
二重線で訂正していただいて結構です。訂正印は不要です。
再発行をご希望の場合は、給付金コールセンターへご連絡ください。
銀行口座を持っていません。どのように受給できますか。
ご事情をお伺いしますので、給付金コールセンターへご連絡ください。
受給した給付金は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
本庄市から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか。
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地が本庄市である場合は、本庄市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
(注意)令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税が本庄市で課税されている方については、支給要件を満たすと本庄市から支給されます。
他市区町村から本庄市に転入しました。どの市区町村から支給されますか。
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地が本庄市である場合は、本庄市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転入前の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
(注意)令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税が本庄市で課税されている方については、支給要件を満たすと本庄市から支給されます。
源泉徴収票の「控除外額」とは何ですか。
「控除外額」は、控除(減税)しきれなかった金額です。
源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
「控除外額」(控除しきれない額)の金額が支給されますか。
源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
「控除外額」=不足額給付額とならない例
・令和6年夏ごろに実施された「調整給付金(当初調整給付)」の対象となっていた場合
・源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合
源泉徴収票の「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか。
実際に定額減税を実施して控除した年調減税額のことです。
令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税については、含まれていないためです。
(参考)定額減税可能額の考え方
・所得税分の定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
・個人住民税分の定額減税可能額1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された「調整給付金(当初調整給付)」の対象ではなかったが、不足額給付の対象になりますか。
令和6年中の収入及び所得税額が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
事業専従者ですが、令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税の所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう「不足額給付2」の対象としています。
このうち、「調整給付金(当初調整給付)」や「低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)」を受給している場合は給付対象となりません。
令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付の支給はありますか。
こどもが生まれた等、扶養親族の数が増えたことにより、令和6年の夏ごろに実施された「調整給付金(当初調整給付)」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
(注意)個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。
住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額を、不足額給付で支給します。
ただし、令和6年の夏ごろに実施された「調整給付金(当初調整給付)」の対象であった場合は、税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額と、「調整給付金(当初調整給付)」の差額が支給されます。
令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。
令和7年1月1日時点で本庄市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。
ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
令和6年の夏ごろに支給された「調整給付金(当初調整給付)」を受け取っていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
「調整給付金(当初調整給付)」を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますが、受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、「調整給付金(当初調整給付)」分を上乗せして受給することはできません。
その他

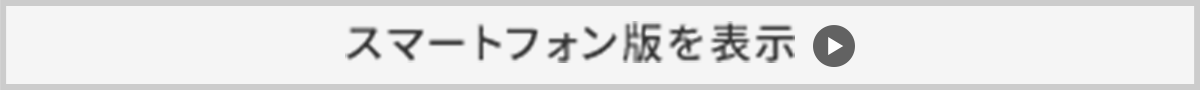







更新日:2025年08月05日