健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
概要
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告するとともに、住民に公表することとなりました。
健全化判断比率とは、次の4つの指標を指し、資金不足比率は水道事業や公共下水道事業などの公営企業ごとに比率を算定します。
- 実質赤字比率
- 連結実質赤字比率
- 実質公債費比率
- 将来負担比率
なお、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合は、財政健全化計画を定めなければならず、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった公営企業は経営健全化計画を定めることとなります。
令和5年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率 (PDFファイル: 177.3KB)
令和4年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率 (PDFファイル: 177.3KB)
令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率 (PDFファイル: 175.0KB)
令和2年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率 (PDFファイル: 175.1KB)
令和元年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率 (PDFファイル: 176.9KB)
健全化判断比率及び資金不足比率の算定式
実質赤字比率
一般会計等(注釈1) の実質的な赤字額が、標準的な収入(標準財政規模(注釈2))に対して、どのくらいの割合になるのかを示す指標です。
実質赤字比率=[一般会計等の実質赤字額] ÷[標準財政規模]
連結実質赤字比率
全会計の実質的な赤字額が、標準的な収入(標準財政規模)に対して、どのくらいの割合になるのかを示す指標です。
連結実質赤字比率=[全会計の実質赤字額]÷[標準財政規模]
実質公債費比率
一般会計等が負担する公債費及びこれに準ずる経費が、標準的な収入(標準財政規模)に対して、どのくらいの割合になるのかを示す指標です。次の算定式で求められた数値の3か年平均を用います。
実質公債費比率=[地方債の元利償還金等(注釈3)-(特定財源+元利償還金等に係る基準財政需要額算入額)] ÷[標準財政規模-元利償還金等に係る基準財政需要額算入額]
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき、公営企業・第三セクター等を含めた本庄市全体の「実質的な負債」が、標準的な収入(標準財政規模)に対して、どのくらいの割合になるのかを示す指標です。
将来負担比率=[将来負担額(注釈4)-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額)] ÷[標準財政規模-元利償還金等に係る基準財政需要額算入額]
資金不足比率
水道事業や公共下水道事業などの公営企業における資金の不足額が、事業の規模に対して、どのくらいの割合になるのかを示す指標です。
資金不足比率=[資金の不足額] ÷[事業の規模]
用語解説
(注釈1) 一般会計等
本庄市では、一般会計・住宅資金貸付事業特別会計を指します。
(注釈2) 標準財政規模
標準的な状態で通常収入されるであろう経常的な一般財源の規模を示すもので、算定式で表すと[標準税収入額等+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額]となります。
(注釈3) 地方債の元利償還金等
一般会計等の元利償還金だけではなく、「一般会計から公営企業に対する繰出金のうち公営企業債の償還に充てたとみなされるもの」や「一部事務組合等に対する負担金のうち当該組合等が起こした地方債の償還に充てたと認められるもの」といった公債費に準ずる経費も含んだものとなります。
(注釈4) 将来負担額
一般会計等の地方債現在高、公営企業債のうち一般会計等からの繰入見込額、一般会計等が負担する退職手当負担見込額、土地開発公社等に対する負担見込額等です。
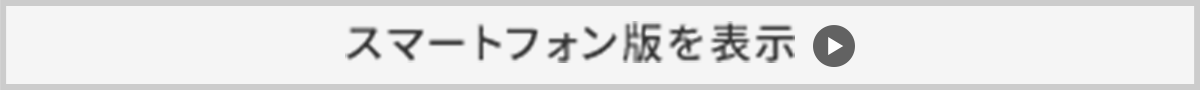







更新日:2024年09月20日