市指定文化財(記念物)
史跡・旧跡(19件)
|
名称 |
所在地 |
|---|---|
|
本庄市中央1-4 |
|
|
本庄市本庄3-5 |
|
|
本庄市栄2-7 |
|
|
本庄市中央3-4 |
|
|
本庄市中央3-3 |
|
|
本庄市小島95-2 |
|
|
本庄市小島3-1 |
|
|
本庄市小島2-11 |
|
|
本庄市児玉町児玉198 |
|
|
本庄市児玉町秋山 |
|
|
本庄市児玉町秋山1769-1 |
|
|
本庄市児玉町小平 |
|
|
本庄市児玉町太駄908-1 |
|
|
本庄市児玉町蛭川214-3 |
|
|
本庄市児玉町入浅見819 |
|
|
本庄市児玉町長沖303-1 |
|
|
本庄市万年寺3-3-7 |
|
|
本庄市中央2-8-26 |
|
|
本庄市児玉町小平 |
小笠原信嶺夫妻の墓

徳川家康に属して活躍した小笠原信嶺は、天正18年(1590)9月に武州本庄城主となりました。信嶺は慶長3年(1598)2月19日に52歳で死去し、生前自ら開基した開善寺に葬られました。夫人も同所に葬られています。墓石は夫妻共に全高が約180センチメートルの宝篋印塔で、戦国末期より近世初期にかけて関東でもよくみられる形状をしています。

戦国時代、児玉党の後裔本庄実忠が弘治2年(1556)に築城したといわれています。本庄氏は関東管領山内上杉氏に従っていましたが、上杉氏没落後は小田原北条氏に属しました。
天正18年(1590)の豊臣秀吉の小田原攻めの際に落城し、その後、徳川家康の関東入国後に家康の家臣小笠原信嶺が1万石で本庄城主となりました。

昭和29年12月、耕作中に地中より土器が発見され、翌年3月から昭和33年まで4回にわたって二本松遺跡1号住居跡として発掘調査が行われました。発掘調査の事例が少ないこの時期にあって学術的に注目された重要な遺跡です。

普寛上人は享保16年(1731)に秩父大滝村に生まれ、34歳の時に天台宗の修験者となり、神道御嶽教を創設しました。行者となり各地の登山道を切り開きますが、中でも寛政4年(1792)に開いた木曾御嶽山の王滝口の開設は有名です。普寛上人は享和元年(1801)に江戸から故郷秩父へ帰る途中本庄宿にて死去しました。

小倉家墓地には江戸時代の有名な文人墨客達の遺墨を刻んだ墓石が多く所在します。小倉家は江戸末期にこの地で料亭「紅葉屋」を営み、小倉紅於は独立して旅籠「小倉屋」を営みました。広大な敷地を持ち、邸宅は小倉山房と呼ばれました。山房亭主は多くの文人たちと交友があり、遺墨を永久に残すため江戸の石工を召抱えました。優れた作品を今に伝えています。

旭・小島古墳群中の1基で、直径約43メートル、高さ約4メートルの円墳です。出土遺物は一部破損していましたが、昭和52年に復元しました。

旭・小島古墳群中の1基で、東西径18メートル、高さ3.5メートルの円墳です。6世紀末頃の築造と推定されます。

旭・小島古墳群中の1基で、直径30メートル、高さ4.5メートルの円墳です。6世紀後半から末頃の築造と推定されます。

旧児玉村の高札場で、現在は八幡神社境内の北西隅にあります。 従来は本町と連雀町の境付近を通っている中山道脇往還川越道の中央にありましたが、交通の障害になるため現在地に移転されました。

秋山古墳群は現在、前方後円墳2基を含む43基の古墳が現存しています。墳丘を失った古墳跡を含めると100基近い古墳があったと推定されます。古墳の分布は秋山地区の塚原・塚間・宿田保に多く所在しています。

秋山古墳群中の1基で、古墳頂上に庚申塔があります。現状では直径16メートル、高さ5メートルですが、発掘調査の結果、直径34メートルで二重の周溝を持つ大型の円墳であることがわかりました。玄室内部から馬具・鉄鏃・鉄刀・弓金具・装身具等の遺物が出土しました。

この岩谷堂は江戸時代に浄土宗僧の浄厳が、一向専修念仏道場を開いた場所といわれています。その時代広く信仰を集め、この地に続く道を岩谷道といい、多くの参詣者がありました。また、石仏寄進も江戸時代から始まり、参道の両脇に多くの石仏が造立されています。石仏寄進は近年も続いており、毎年春に万霊供養祭が開かれています。

太駄村の高札場で秩父道と上州道の分岐点という交通の要所にあります。高札場が所在する字殿谷戸は旧太駄村のほぼ中央に位置していて、秩父方面と上州鬼石、児玉八幡山方面の分岐点にあたります。

一の谷の合戦で児玉党の庄四郎高家に生け捕られた平清盛の五男平三位中将重衡の首塚です。捕らえられた重衡は鎌倉に送られて源頼朝に面会した後、南都の僧兵に引き渡されました。その後、処刑された重衡の首を、庄高家は自分の領地蛭河郷に持ち帰り、手厚く供養したといわれています。蛭川の駒形神社の隣の釈迦堂墓地にあります。

墳丘上に金鑚神社が鎮座しています。墳丘は直径67.6メートル、高さ約7メートルで、周溝を含めると100メートルを超える大型の円墳です。古式古墳調査で、出土した円筒埴輪には、類例の少ない表面に格子目叩きを持つものが出土しました。

長沖古墳群中の1基で、全長32メートル、高さ3メートルの前方後円墳です。古墳群中でも中心的な古墳であり、円筒埴輪や朝顔形円筒埴輪等が出土しました。

旭・小島古墳群中の1基で、墳形は周堀を含む一辺が33.5メートルの方墳と推定されています。現状では墳丘が大きく削り取られていますが、5世紀初頭頃の方墳として珍しいものです。

小笠原信之は酒井忠次の三男で、少年の頃より徳川家康に仕えていました。小笠原信嶺の娘を娶り養嗣子となり、家督を継いで二代本庄城主となります。十数年の間、城主として中山道の整備など本庄宿の発展の礎を築きました。

標高531メートルの陣見山山頂部から北に伸びる尾根一帯を陣見平と呼びます。天正18年(1590)に豊臣氏方の軍勢が北条氏方の八幡山城(雉岡城の別名)を攻めた時に、この山に登り城内の陣列を確かめたという話が伝わっています。
天然記念物(11件)
|
名称 |
所在地 |
|---|---|
|
本庄市本庄3-5 |
|
|
本庄市千代田3-2-3 |
|
|
本庄市中央1-5-2 |
|
|
本庄市東富田50-1 |
|
|
本庄市沼和田869 |
|
|
本庄市山王堂228-1 |
|
|
本庄市沼和田926 |
|
|
本庄市児玉町保木野387 |
|
|
本庄市児玉町児玉1746 |
|
|
本庄市児玉町小平1 |
|
|
本庄市児玉町児玉198 |
城山稲荷神社のヤブツバキ

城山稲荷神社は本庄城主本庄宮内少輔実忠勧請と伝えられ、西本庄の地にあった椿稲荷を現在地に移転したという社伝が残っています。目通り周囲は1.2メートルです。

社伝によれば、関宿城主小笠原忠貴が社殿建立の際に植樹したと伝えられています。目通り周囲は3.4メートルです。

愛宕神社は古墳上に祀られ、社殿に至る石段の左手に神木として所在しています。ケヤキは南北に2本立ちとなっていて、南樹は目通り周囲4メートル、北樹は目通り周囲4.3メートルです。

本庄城主小笠原氏が赤城山麓より100本の松を取り寄せて、城内及び領内に植えたと伝えられており、この松のみが生き残ったといわれています。目通り周囲は2.6メートルで、東西に枝を広げていますが、その長さは20メートルにも及んでいます。

宝輪寺は天正年間の開基と伝えられています。本堂の西側の墓地に接してカヤがあり、目通り周囲は4.9メートルです。

日枝神社の創立は江戸時代の慶長期以前と伝えられています。同社のケヤキは利根川堤防沿いに所在しており、その創立期に遡ると推定されています。目通り周囲は5.4メートルです。

飯玉神社境内に所在しており、目通り周囲は3.2メートルです。

龍清寺本堂の左前に所在しています。その形がまさに龍神が飛び立とうとしている様に似ていることから、「飛龍のカヤ」とも呼ばれています。目通り周囲は4メートルです。

児玉思池親水公園内にあり、3本のマルバヤナギがまとまって自生しています。いずれも古木で、2本は幹回りが3メートル弱あり、1本は2メートルを超えています。市内ではマルバヤナギの分布は大変珍しく、貴重な樹木です。

ケヤキは社殿の右側にあり、目通り周囲は5メートルです。スギは社殿の左側奥にあり、目通り周囲は4.6メートルです。
社殿の両脇にそびえるケヤキとスギの古木は、児玉地域で最大の樹木となっています。
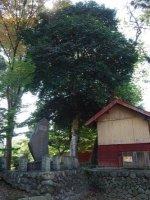
八幡神社はかつて境内一円が樹木で覆われていましたが、事情により失われた古木も多くありました。しかし、現在でもケヤキ等の古木が残されており、社叢林を構成しています。






更新日:2025年01月29日