国民健康保険税
国民健康保険税とは
1.国民健康保険税
国民健康保険の保険料にあたるものです。医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの国民健康保険事業に充てられます。
2.納税義務者
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に加入している人がいれば、納税通知書は世帯主に郵送されます。
3.税額の計算方法
4月から翌年3月までの12か月を1年度として税額を計算します。税額は、加入者数、前年の所得金額、当年度の固定資産税額をもとに計算されます。年度途中で加入・脱退した場合などは、加入月数に応じて月割り計算となります。
所得の情報はその年の1月1日に住んでいた自治体が保有しています。本庄市へ転入された方の場合、その自治体へ所得の照会をするため、照会の結果により後から税額が変更になる場合があります。
4.国民健康保険税の納期
納期は7月から翌年2月までの年間8回です。12か月分を8回の納期に分けているため、1期分が1か月分の税額ではありません。
国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(注意1,2)を合算して年間税額を算出します。
(注意1) 40歳から64歳までの人は介護保険の第2号被保険者となり、介護納付金分が課税されます。なお、障害者支援施設等に入所(入院)している方については、介護保険第2号被保険者とならないため、届出により介護納付金分が課税されなくなります。(入所または入院している施設が障害者支援施設等に該当するかは介護保険課へお問い合わせください。)
(注意2) 年度途中で40歳になる人は、誕生月の分から(1日が誕生日の人は前月分から)課税されます。
令和7年度の税額・税率
医療給付費分
- ア 所得割 国保加入者の前年中の所得から基礎控除43万円を引いた額の合算額×6.9%
- イ 資産割 国保加入者の固定資産税額(都市計画税は除く)の合算額×20.0%
- ウ 均等割 国保加入者1人あたり19,500円
- エ 平等割 1世帯あたり16,000円
ア+イ+ウ+エ=医療給付費分年間税額
備考:アからエの合計額が660,000円(課税限度額)を超えた場合、超えた部分は切り捨て
後期高齢者支援金分
- オ 所得割 国保加入者の前年中の所得から基礎控除43万円を引いた額の合算額×2.9%
- カ 均等割 国保加入者1人あたり9,900円
オ+カ=後期高齢者支援金分年間税額
備考:オとカの合計額が260,000円(課税限度額)を超えた場合、超えた部分は切り捨て
介護納付金分
- キ 所得割 国保加入者の前年中の所得から基礎控除43万円を引いた額の合算額×2.7%
- ク 均等割 国保加入者1人あたり12,400円
キ+ク=介護納付金分年間税額
備考:キとクの合計額が170,000円(課税限度額)を超えた場合、超えた部分は切り捨て
令和7年度の国民健康保険税をご自分で試算することができます。
令和7年度国民健康保険税計算シート (Excelファイル: 20.2KB)
(注意) あくまで試算であり、実際の税額とは異なる場合がありますのでご了承ください。
年度途中で国保に加入(脱退)した場合
例えば10月に加入した場合は、翌年3月までの6か月分が課税されますので、次のとおり計算されます。
課税額 = 年間税額 × 6/12
算出方法、税率、納期等は市町村ごとに異なります
国民健康保険税の算出方法については、地方税法および各市町村の条例により定められています。そのため、転入や転出により住所地の市町村が変わると、それぞれの市町村の税率で算出されることになります。
令和6年度までの税額・税率は以下からご覧ください。
令和6年度までの税額・税率 (Wordファイル: 37.1KB)
国民健康保険税の軽減制度について
1.低所得世帯に対する軽減制度
世帯主・国保加入者・特定同一所属者の合計所得(軽減判定所得)が、法令に定められた額よりも低い場合には、均等割と平等割が軽減されます。
軽減の適用を受けるには、世帯主・前年度の1月1日現在で16歳以上の国保加入者・特定同一所属者の所得の申告が必要です。未申告の人がいると軽減の適用を受けることはできません。収入が無かった人、扶養に入っている学生や、障害年金・遺族年金等の非課税年金のみを受給している人も申告が必要ですのでご注意ください。
注意1
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を脱退した人のうち、以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に属する人です。
注意2
軽減判定所得は、以下の点で国民健康保険税を算定する際の所得金額と異なります。
- 基礎控除43万円控除前の額
- 前年中の公的年金等に係る所得について、65歳以上の者に係る公的年金等控除額の適用を受けた年金所得者については年金所得から15万円(年金所得が15万円以下の場合にはその全額)を控除した額
- 分離譲渡所得金額については特別控除をする前の額
- 事業専従者控除を受けている事業主は専従者控除をする前の額
(専従者については専従者給与の部分は軽減判定所得に含まれません。)
|
軽減区分 |
軽減基準額 |
|---|---|
| 7割軽減 |
軽減判定所得が43万円+{(※給与所得者等の数-1)×10万円}以下の世帯 |
| 5割軽減 |
軽減判定所得が43万円+{(※給与所得者等の数-1)×10万円}+{30.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)}以下の世帯 |
| 2割軽減 |
軽減判定所得が43万円+{(※給与所得者等の数-1)×10万円}+{56万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)}以下の世帯 |
※世帯における、一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))の人数。{(給与所得者等の数-1)×10万円}部分は、該当者が2人以上の場合に適用となります。
令和6年度までの軽減基準は以下からご覧ください。
令和6年度までの軽減基準 (Wordファイル: 18.6KB)
2.後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯への軽減制度
世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が1人になる世帯は、世帯構成が変わらなければ、5年間は平等割が半額に、続く3年間は4分の3の額になります。
3.旧被扶養者に対する減免制度
社会保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者だった65歳から74歳までの人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、納期限7日前までの申請により減免が受けられます。
減免内容
- 所得割・資産割 全額免除
- 均等割 2分の1減額
- 平等割 2分の1減額 (旧被扶養者のみで構成されている世帯に適用)
減免期間
- 所得割・資産割 国保喪失まで
- 均等割・平等割 2年間
必要なもの
- マイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書
4.会社都合による離職者への軽減制度
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)である場合は、申請により国民健康保険税が軽減されます。
対象者の条件
平成21年3月31日以降に離職した人のうち、失業等給付を受けている人(受けていた人)で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する人
(注意) 雇用保険の受給資格がない人、または65歳以上で離職された人は対象になりません。
(注意) 「特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」をお持ちの人は対象になりません。
軽減内容
対象者の給与所得を100分の30として国民健康保険税の計算をします。
(注意) 給与所得以外の所得は軽減対象になりません。
(注意) 対象者以外の人の給与所得は軽減対象になりません。
軽減期間
開始時期:離職日の翌日の属する月
終了時期:開始時期の属する年度の翌年度末まで又は新たな被用者保険に加入した国保喪失日のいずれか早い日
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知書
- マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかる書類
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
5.未就学児に対する軽減制度(※令和4年度から開始)
未就学児に係る国民健康保険税のうち均等割額の2分の1を減額します。
1の低所得世帯に対する軽減制度が適用される世帯の未就学児は、当該軽減後の均等割額を2分の1減額します。
令和7年度は、平成31年4月2日以降に生まれた人が対象です。
※申請は不要です。
|
軽減区分 |
未就学児に対する 軽減後の均等割額 |
|---|---|
|
7割軽減 |
4,410円 |
|
5割軽減 |
7,350円 |
|
2割軽減 |
11,760円 |
|
軽減なし |
14,700円 |
※表中の均等割額は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の合計額です。
※実際の均等割額は、100円単位での課税となるため、軽減後の端数が異なる場合があります。
6.産前産後期間の減額制度(※令和6年1月から開始)
国民健康保険に加入されている人が出産予定または出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税のうち所得割額および均等割額を減額します。
産前産後保険税減額リーフレット(PDFファイル:513.7KB)
対象となる人
国民健康保険被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の人
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産(人工妊娠中絶も含む)、早産の場合も含みます。
対象期間
- 出産予定日または出産月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合は出産月の3か月前から6か月間
対象内容
出産予定または出産した人の国民健康保険税のうち所得割額及び均等割額
※令和5年度分においては、令和6年1月以降分が減額の対象となります。
※国民健康保険税が課税限度額に達している世帯については、減額制度を適用しても税額が変わらない場合があります。
届出
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
※届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。ただし、確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。
必要なもの
- 出産(予定)日が確認できるもの(母子手帳など)
- 多胎妊娠の場合は、その事実が確認できるもの(母子手帳など)
- 死産の場合は、死産証明書など
- 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
※出産後に届出をするときは、出生証明書等の出産日及び親子関係を明らかにする書類(住民票、戸籍謄抄本等)が必要な場合があります。
※別世帯の人が届出をする場合は委任状が必要です。
国民健康保険税の減免
国民健康保険税は、加入者の所得や資産状況に応じて負担するものですが、火災や天災などで財産に大きな損害を受けたとき、所得が皆無となったため生活が著しく困難になったときなど、預貯金などの利用できる資産を活用しても納付が困難になった際は、申請により減免を受けられる場合があります。(本庄市国民健康保険税条例第25条)
詳しくは保険課へご相談ください。
納付方法
国民健康保険税は、普通徴収または特別徴収(年金からの天引き)で納付します。
普通徴収
口座振替または納付書払い
口座振替について
本庄市では普通徴収の納付を原則、口座振替としています。保険課では、専用の端末機にキャッシュカードを通して暗証番号を入力するだけで口座振替の登録ができますので、ぜひご利用ください。
登録可能な金融機関
- 埼玉りそな銀行
- 群馬銀行
- 足利銀行
- 武蔵野銀行
- 東和銀行
- しののめ信用金庫
- 埼玉縣信用金庫
- 中央労働金庫
- 埼玉ひびきの農協
- りそな銀行
- みずほ銀行
- ゆうちょ銀行
- 埼玉信用組合(注意)
(注意) 埼玉信用組合については金融機関の窓口で口座登録の手続きができます。手続きには通帳と届出印が必要です。
納付書払いについて
コンビニなどで納付することができます。納付書は期別ごとに一枚一枚分かれています。期別の取違いのないよう納付書に記載されている期別と納期限をよくお確かめのうえ、必要な納付書だけをお持ちになって納付してください。
普通徴収の納期
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
(注意) 口座振替は月末に引き落とします。(月末が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌月の営業初日)
納付方法については、以下のリンクもご覧ください。
特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収は、世帯主が受給している年金から天引きする納付方法です。次の条件をすべて満たしている世帯は、自動的に特別徴収へ切り替わります。
- 世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給していること
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、公的年金受給額の2分の1を超えないこと
(注意) 世帯主や世帯員が年度途中で75歳になる場合には、その年度の特別徴収を行うことができないため、普通徴収の納税通知書を郵送します。
(注意) 特別徴収になった場合でも、申請により口座振替に変更することができます。(手続きについてはページ下部をご覧ください。)
特別徴収の納期
- 4月
- 6月
- 8月
- 10月
- 12月
- 2月
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更を希望する場合
特別徴収の対象となった人は、希望により普通徴収(口座振替のみ)を選択できます。納付書による納付は選択できません。
必要なもの
- キャッシュカード(登録可能な金融機関は普通徴収の項目をご参照ください。)
- 納付方法変更申出書(PDFファイル:43.2KB)
※現在口座振替で納付している人は、キャッシュカードは不要です。
| 特別徴収(年金から天引き) | 普通徴収(口座振替) | |
| 回数 | 年6回 | 年8回 |
| 納付月 |
4・6・8月(仮徴収) 10・12・翌年2月(本徴収) |
7月から翌年2月までの各月 |
| 納付額 |
前年度の税額を参考に4・6・8月(仮徴収※)で納付し、当年度の税額が決定した後、仮徴収額を差し引いた残額を10・12・翌年2月(本徴収)で納付。 ※特別徴収開始年度のみ、前年度の税額÷6=仮徴収税額となります。以降は、2月の本徴収税額を次年度の仮徴収税額とします。
例:年税額が前年度12万円、当年度18万円の場合。 4・6・8月→各2万円 10・12・翌年2月→各4万円 |
当年度の税額を納付月数で割った額。
例:年税額が18万円の場合。 7月→2万6千円 8月から翌年2月まで→各2万円 8月以降の納期に千円未満の端数がある場合、端数は最初の納期に加算されます。 |
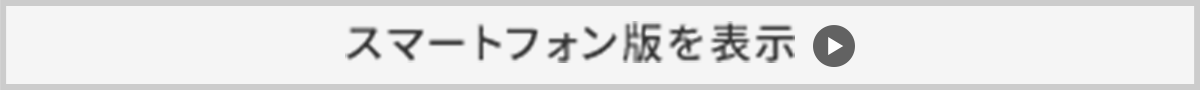







更新日:2024年12月02日