ふるさと納税制度について
ふるさと納税制度とは
ふるさと納税制度とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除される制度です(一定の上限はあります)。また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
ふるさと納税に係る指定制度について
令和元年6月1日以降、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除)の対象となる団体を総務大臣が一定の基準に基づき指定することになりました。
対象となる団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る総務大臣の指定』を参照してください。
※この制度は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。
所得税から控除される額
2,000円を超えた金額が所得控除されます。
寄附金控除額
寄附金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円
個人住民税から控除される額
基本控除額と特例控除額の合計額が税額控除されます。
基本控除額
(寄附金額(総所得金額等の30%が限度)-2,000円)×10%
特例控除額
※総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金が対象となります。
(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)
平成26年度から令和20年度まで復興特別所得税分を加算するため、計算式は下記のものを使用します。
(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
ふるさと納税を行った場合
ふるさと納税を行い寄附金控除を受けるためには、確定申告または住民税申告が必要となります。なお、平成27年度税制改正により、一定の要件に該当する方がふるさと納税を行った場合は、確定申告や住民税申告を行わなくても寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
寄附金控除を受けるための手続き
お住まいの住所地を管轄する税務署で確定申告を行ってください。(ただし、所得税が非課税で住民税のみ課税となる方は、寄附をした翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に寄附金控除の申告を行ってください。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等が、都道府県または市区町村に対し寄附を行う際、5団体以内であれば寄附先の団体に特例の申請をすることで、確定申告や住民税申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。この特例を受けた場合、翌年度の個人住民税から所得税の軽減相当額を含めて控除されます。(平成27年4月1日以降に行われた寄附から適用)
なお、以下の項目に該当する場合は特例の適用は受けられません。
- 寄附先が6団体以上ある場合
- 確定申告又は住民税申告を行った場合
- 住所変更等の理由により申請した内容に変更のあった方が、翌年1月10日までに寄附先の団体へ変更届出書を提出していない場合
ワンストップ特例による住民税の寄附金控除を受けることができない場合は、「ふるさと納税による住民税控除不適用のお知らせ」を送付しますので、内容を確認の上、必要に応じて確定申告又は住民税申告を行ってください(寄附金控除にワンストップ特例分を含めて確定申告又は住民税申告を行った場合は、再度の申告は不要です)。
参考リンク集
ふるさと納税についての詳細は、下記のホームページをご参照ください。
本庄太郎さんの場合(モデルケースによる説明)
本庄太郎さんは、前年に給与収入が500万円あり、応援したい市へ10万円を寄附しました。会社で行われた年末調整では妻を扶養にとり、所得税及び復興特別所得税は176,100円を源泉徴収されました。
所得税から控除される額
所得税は所得金額から所得控除を引いて算出した課税総所得金額に税率をかけ、税額控除を引いて求めます。
給与所得 給与収入5,000,000円-(給与所得控除5,000,000円×20%+440,000円)=3,560,000円(参考:国税庁「給与所得控除」)
合計所得金額 3,560,000円…(ア)
配偶者控除380,000円+寄附金控除(100,000円-2,000円)+基礎控除480,000円=958,000円
所得控除額合計958,000円…(イ)
課税総所得金額 (ア)-(イ)=2,602,000円
所得税額及び復興特別所得税額
課税総所得金額が1,950,000円~3,299,000円の税率は10%、控除額は97,500円です。(参考:国税庁「所得税の税率」)
また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までは復興特別所得税として所得税の2.1%が加算されます。
(2,602,000円×10%-97,500円)×1.021=166,100円(100円未満切捨て)
還付される額
源泉徴収税額176,100円-166,100円=10,000円
よって、所得税からは10,000円の還付が受けられます。
個人住民税から控除される額
個人住民税は所得割と均等割の合計したものを年間の税額としています。
所得割は所得税と同様に、所得金額から所得控除を引いて算出した課税標準額に市民税6%と県民税4%の税率をかけ、税額控除を引いて求めます。
合計所得金額 3,560,000円…(ア)
配偶者控除330,000円+基礎控除430,000円=760,000円
所得控除額合計 760,000円…(イ)´
課税標準額 (ア)-(イ)´=2,800,000円
- 市民税所得割 2,800,000円×6%=168,000円
- 県民税所得割 2,800,000円×4%=112,000円
所得割から税額控除を引きます。調整控除は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)です。(参考:本庄市「個人住民税(市民税・県民税)」)
- 市民税 168,000円-調整控除1,500円=166,500円
- 県民税 112,000円-調整控除1,000円=111,000円
調整控除を引いた後、寄附金税額控除を引きます。
寄附金税額控除
寄附金税額控除は基本控除額と特例控除額を合計して求めます。
基本控除額
- 市民税 (100,000円-2,000円)×6%=5,880円
- 県民税 (100,000円-2,000円)×4%=3,920円
特例控除額
(100,000円-2,000円)×{90%-(10%×1.021)}=78,195円(小数点以下切上げ)…(ウ)
平成28年度以降の特例控除額の控除限度額は住民税所得割の2割。
特例控除額の控除限度額 277,500円×20%=55,500円…(エ)
(ウ)>(エ)のため特例控除額は55,500円
- 市民税 55,500円×60%=33,300円
- 県民税 55,500円×40%=22,200円
寄附金税額控除
- 市民税 基本控除額5,880円+特例控除額33,300円=39,180円
- 県民税 基本控除額3,920円+特例控除額22,200円=26,120円
よって、個人住民税からは65,300円の税額控除が受けられます。
所得割額
調整控除を引いた後の個人住民税所得割額から寄附金税額控除を引いて所得割額を求めます。
- 市民税 166,500円-寄附金税額控除39,180円=127,300円(100円未満切捨て)
- 県民税 111,000円-寄附金税額控除26,120円=84,800円(100円未満切捨て)
均等割額
均等割額は市民税3,000円、県民税1,000円です。
年間で納める個人住民税額
上記で求めた所得割額と均等割額を合計します。
-
市民税 127,300円+3,000円=130,300円
-
県民税 84,800円+1,000円=85,800円
合計 216,100円
個人住民税は前年の所得に対し課税されるため、還付ではなくその年度に納める税額から控除されます。本庄太郎さんは所得税10,000円と個人住民税65,300円、合わせて75,300円が軽減されることになりました。
本庄市へのふるさと納税
本庄市への寄附を検討されている方は下記のページをご参照ください。
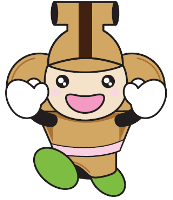






更新日:2024年11月14日